2025/10/09
矯正治療における大臼歯の抜歯について
こんにちは。姫路はま矯正歯科 院長の濱です。
これまでのブログでは、矯正治療に伴う抜歯についてお話してきましたが、今回はその中でも少し特殊なケース 「大臼歯の抜歯」について詳しくご説明したいと思います。
人間の口の中には、第一大臼歯(6番)と第二大臼歯(7番)の2種類の大臼歯があります。これらは上顎と下顎の両方に存在し、咬合(かみ合わせ)において非常に重要な役割を果たしています。では、矯正治療において、どのような場合に大臼歯を抜歯する必要があるのでしょうか。
第一大臼歯(6番)の抜歯について
まず、第一大臼歯、いわゆる「6番」の抜歯についてです。
実は矯正治療において、この6番を抜歯することはほとんどありません。
なぜかというと、第一大臼歯は「キー・トゥース(Key Tooth)」と呼ばれるほど、咬み合わせの軸となる非常に大切な歯だからです。同じく犬歯(3番)もキー・トゥースの一つであり、これらの歯は歯列全体の安定性に深く関わっています。そのため、よほどの理由がない限り、3番と6番は抜歯しないのが原則です。
しかし、例外的に抜歯を検討するケースもあります。
それは、虫歯が非常に大きく、歯の保存が不可能な場合です。このような場合には、機能的にも審美的にも残すことが難しいため、やむを得ず抜歯を行います。
問題となるのは、抜歯後の「スペース(歯のあった空間)」の扱い方です。
第一大臼歯の幅はおおよそ12mmあり、矯正治療でこのスペースをすべて閉じるのは現実的に困難です。ごく稀に閉鎖できることもありますが、治療期間が非常に長くなってしまいます。
そのため、抜歯後のスペースをどのように補うかを慎重に検討する必要があります。主な方法は次の3つです。
-
インプラントによる補綴
欠損部にインプラントを埋入し、咬合を回復させる方法です。機能的にも長期的にも安定します。 -
ブリッジによる補綴
両隣の歯を支台として被せ物を行う方法です。インプラントが難しい場合に選択されます。 -
親知らずの移植
親知らず(智歯)が健全に生えており、スペースや形態が適合する場合には、移植することも可能です。
このように、第一大臼歯の抜歯は非常に慎重に判断し、抜歯後の補綴計画を含めてトータルで考える必要があります。
第二大臼歯(7番)の抜歯について
次に、第二大臼歯(7番)の抜歯についてです。
第一大臼歯に比べると、7番を抜歯するケースはやや多いといえます。
① 親知らずを有効利用するケース
1つ目のケースは、親知らず(8番)を活かすために7番を抜歯する場合です。
親知らずが良好な位置にまっすぐ生えている、あるいは萌出途中で利用できそうな場合、7番を抜歯して8番を手前に移動させることができます。
この方法では、親知らずを「使える歯」として活用でき、将来的に不要になる可能性のある歯を抜かずに済むという利点があります。矯正治療における抜歯本数を減らしたい場合にも有効な選択肢です。
② 遠心移動を大きくしたいケース
2つ目のケースは、上顎の歯列を後方(遠心方向)に大きく移動させたい場合です。
たとえば、骨格性上顎前突(上顎が前方に出ているタイプ)の患者様では、上顎の前後差を矯正でカモフラージュする必要があります。
小臼歯(4番)抜歯だけでは移動量が足りない場合、7番も抜歯してスペースを確保し、全体をさらに後方に移動させることで咬合を整えます。
このような治療では、歯科矯正用アンカースクリューを併用して、効率的に歯列を移動させることが多いです。
ただし、下顎の第二大臼歯を抜歯して大きく遠心移動するのは、骨の厚みなどの制約からあまり現実的ではありません。主に上顎での選択肢と考えられます。
また、骨格性のズレが大きすぎる場合には、矯正単独では限界があり、外科的矯正(手術併用)を検討する必要もあります。治療開始前にはセファロ分析やCTによる骨の評価を行い、移動可能な範囲や骨格の特徴を十分に把握することが欠かせません。
さらに、遠心移動が大きくなると治療期間も延びますので、患者様と十分に相談し、時間的な見通しを立てた上で治療計画を立てることが重要です。
まとめ
大臼歯の抜歯は、矯正治療の中でも非常に慎重な判断が求められるケースです。
特に第一大臼歯は咬合の要であるため、可能な限り残すことを基本とし、やむを得ない場合のみ抜歯を行います。
第二大臼歯の抜歯は、親知らずの利用や遠心移動の必要性といった治療目的に応じて検討されます。
いずれの場合も、抜歯の可否は「その歯だけ」で判断せず、全体のバランス・骨格・治療計画を総合的に見て決めることが大切です。
大臼歯の抜歯を検討されている方や、治療計画に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
当院ではCTやセファロ分析を用いた正確な診断のもと、最適な治療方針をご提案しています。
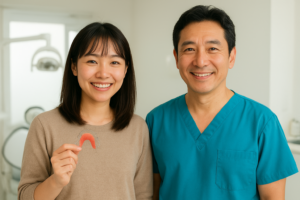
関連記事
|
2025.12.25 小児の受け口(反対咬合)はいつ治す?年齢別にわかる治療法と注意点 |
|
2025.12.18 矯正治療で使うアンカースクリューとは?効果・痛み・リスクを専門医が説明 |
|
2025.12.11 取り外し式との違いは?固定式矯正装置のメリット・デメリットをプロが解説 |